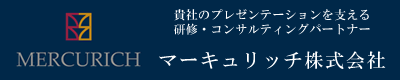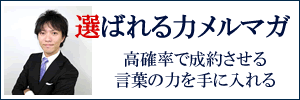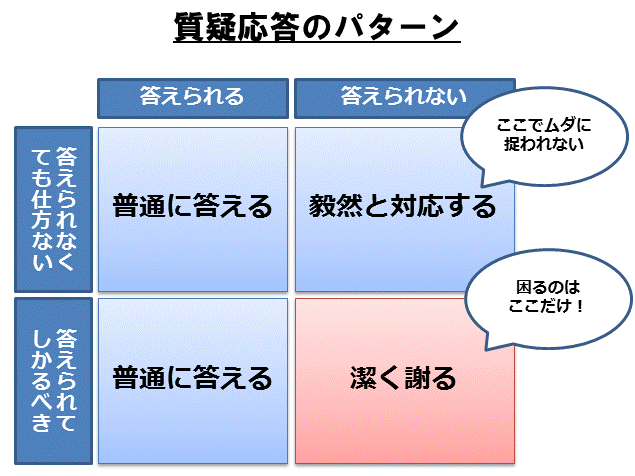■山崎豊子さんに学ぶ、プレゼンテーションをつくりあげる際の姿勢
 作家の山崎豊子さんが、2013年9月29日にお亡くなりになりました。
作家の山崎豊子さんが、2013年9月29日にお亡くなりになりました。
山崎豊子さんといえば、白い巨塔や沈まぬ太陽、華麗なる一族などの名作を生み出した方。
全17作品すべてがベストセラーとなり、うち14作品が映像化されているそうです。
そして、彼女は“取材の鬼”として有名だったそうです(私は、テレビで知りました)。
徹底的な取材があったからこそ、上記のリアリティのある作品が書けたのでしょう。
そして、取材にもとづいた真実を感じさせたからこそ、社会に影響を与えたのでしょう。
取材は、鬼の呼び名のとおり、質も時間も相当なものだった。
取材の相手が「もう、これ以上は聴かれても何にも出ませんって」とひるむほど。
「あなたがしっかり答えてくれなければ、私は小説が書けません!」気迫がすごかったそうです。
■取材の鬼になったつもりで、しっかり聞き出す
この話を聞いて、思いました。
プレゼンをつくるときも同じだと。
私の場合、マンツーマンのご指導のときは、コンテンツつくりからサポートします。
色々とインタビューをしながら、プレゼンで話すに値するネタを引き出すわけです。
ネタがスムーズに出てくることもあれば、かなりの産みの苦しみがあるときもあります。
そして、産みの苦しみがあるとき、判断が求められます。
もっと掘れば出てくるのか?
それとも、もう掘り切っているのか?
ただ掘れば良いというわけではない。
けれども、多くの場合はもっと掘り下げれば、最高のコンテンツが出てきたりする。
インタビュー相手を信じて、聴き切ることが大切だと思うのです。
■自分で考える場合も、自己取材の鬼になったつもりで
これは、他者にインタビューする場合に限った話ではありません。
自分でプレゼンの内容を考える際も、自分に取材するつもりでやってみる。
つまり、自分にたくさんの質問を投げかける。
・そのメッセージの根拠は何ですか?
・それは、確実に正しいことなのですか?
・それ以外のアイデアはありませんか?
・そこから導かれる結論は何ですか?
…など。
ここを、突き詰められる人と、安易に目の前のアイデアに逃げる人では、語る内容の質が全然違う。
きっと、山崎豊子さんもそんな気持ちだったのだと思います。
インタビューがすすんでいくと「まぁ、これくらいネタが集まったら、そこそこ書けるだろう」と感じる。
そこで切り上げるのか、更にネバって引き出す努力をするのか?
きっと、後者を選ぶ方だから、取材の鬼なんて呼び名になったのでしょう。